父親の病がきっかけで親元就農
アスパラガスと米の複合栽培
適正な栽培面積
YOZE FARM代表の後藤啓介(ごとう けいすけ)さんに、就農までの経緯やアスパラガス栽培、今後の目標について伺いました。
父親の病がきっかけで親元就農
 管理人
管理人後藤さんは就農前にどんな仕事をされていましたか?



大学卒業後に、都内のEコマースを運営するマザーズ上場企業で働いていました。
コールセンターや広告営業、海外事業の業務など、色々な部署で仕事をしていましたが……
最後に就いた総務人事課で給与の査定をしていた時に、会社からの自分の評価や同僚の給与まで全て見えてしまって……
数十年後の将来までが見えてしまったように感じて、仕事への情熱が冷めていってましたね。



人事の仕事の辛い部分なんですね……。
会社を辞めて農業をする予定は、当時はあったのですか?



私は設備業と稲作をしている兼業農家の一人っ子でしたから、「いつかは実家や農業機械などの固定資産の整理は自分がしないといけない」とは考えていました。
だけどすぐに農業がしたいとも思っていなくて、かといって会社員をこの先も続けていくイメージも湧かなかったので、2013年頃は悩んでいましたね。



そこから2014年に就農されたそうですが、悩んでいた仕事を辞めて就農するきっかけがあったのですか?



父親の病気が発覚し、今後の父親の体調はどうなるかが分からない状況になったんです。
2013年は会社に勤めながら田植えを手伝っていましたが、2014年に仕事を辞めて米の栽培全般を手伝うようになりました。
父親が亡くなった2015年の秋から本格的に独立就農して、私が主になって農業をしています。





そうでしたか……。
思いがけないタイミングでの就農になりましたが、ご家族や周囲の反応はどうでしたか?



父親の病態が分かる前から、いずれ農業をするかもとは、当時から付き合っていた妻には伝えてはいました。
それでもいざ栃木に帰って就農すると決めた時、結婚もしてくれて、さらに一緒に農業をしてくれて。
私の都合についてきてくれた妻には、本当に感謝しています。



新しい挑戦を一緒にしてくれるパートナーの存在は、心強かったでしょうね!
お父さまに米栽培を一年教えてもらった期間があるとのことですが、農業のスタートは順調でしたか?



いや、全く順調には進まなかったですね。
私がトラクターの扱いに慣れていなくて、ドライブハロー(田んぼを耕す折りたたみのロータリー)を開きっぱなしのまま走ってしまって圃場近くの民家の外壁にぶつけたり……
ロータリーを何度もぶつけたせいで、PTO(ロータリー部分の回転軸)の調子が悪くなって、諸々で100万円くらいの修理代がいきなりかかりました。



いきなり100万円の修理代はきつい!
不安になる気持ちも分かりますね……。



もう当時は神様に農業をやるなと言われているように感じましたよ(笑)
それでもサラリーマンに戻る気はゼロだったので、農業で生計を立てるしかないなと思っていました。
米+アスパラガスで就農をスタート



後藤さんが就農してから、米とアスパラガスを組み合わせた栽培を始められたそうですね。
従来からの米栽培に加えて、アスパラガスを取り入れられた理由はなんですか?



大田原市は関東一の米処ではありますが、米の価格が下がってきていた当時は、米だけの栽培だとリスクがあると私は考えていました。
周りにも米と施設野菜を組み合わせる栽培スタイルが多いので、米の作付面積を減らして、私もイチゴがアスパラガスを新たに栽培しようと考えていましたね。





なるほど、米の産地でも複合経営が少なくないんですね。
ではイチゴではなく、アスパラガスを選んだ決め手はあったのですか?



近所にイチゴ農家の知り合いがいたので、米+冬のイチゴという組み合わせも最後まで選択肢にはありました。
イチゴなら米との作業ピークがあまり重ならないですし、年中仕事が作れますからね。
それでもアスパラガスを選んだ決め手は、父の知り合いから「アスパラガスのハウス栽培は儲かるぞ!」と勧められたからです。
アスパラガスは大田原市のメジャーな作物ですし、米との複合栽培も私の地域では一般的でしたから。
アスパラガス農家の師匠の話を聞く限り、イチゴよりも時間の余裕が作れそうだと思ったので、アスパラガスにしました。



アスパラガスって、時間のゆとりができる作物なんですね。
毎日アスパラガスを収穫しても、追いつかないイメージでした。



いや、当時は農業のことは分からなかったですし、師匠のアスパラガス栽培がゆとりがあるように見えていただけでしたね。
実際に自分でアスパラガスを栽培してみると、スローライフはただの幻想でした。
現在は4月~10月まで、朝5時からほぼ休日なく働いていますからね(笑)





……めちゃくちゃハードワークですね…!
11月から3月までは仕事に余裕ができるとはいえ、毎日ハウスに通うのはしんどくならないですか?



農繁期の期間だけみれば、がっつり働いてしまってますね。(笑)
でもアスパラガス中心の生活リズムに体が慣れてしまっていますし、今は仕事と私生活の境目がほぼないので、サラリーマン時代ほどのストレスはないんです。
父親の病気がきっかけで農業を始めたこともあって、就農当初は「働きすぎないことへの憧れ」が強かったんですけど……
冬はわりとのんびりと充電できていますし、私にとっては適切な規模と働き方に近いのかもしれません。



どの作物にも農繁期はありますから、後藤さんにとっては、アスパラガスが向いていたということでしょうか。
ところで、ビニールハウスの建設費用はどのように工面されたのですか?



米の栽培面積をを減らしていく中で、自宅から遠い田んぼを売却しました。
1haで500万円くらいで売れたので、その資金でハウスの水源になる井戸の採掘費用に充てました。
井戸の採掘費は、23mくらい掘って加圧タンク込みで、370万円くらいでしたね。
あとは新規作物を開始して独立するということで、当時の経営開始型の補助金を利用して、アスパラガスのハウスを新設できました。
就農準備資金・経営開始資金:農林水産省



田んぼをまとめて売った資金を、アスパラガスに投資したんですか!
補助金も活用されたとはいえ、やっぱり先に犠牲にするものがあったのですね。


現在のアスパラガス栽培



現在の栽培作物と規模、労働力を教えてください。



ハウスのアスパラガスが7反、ホワイトアスパラガスが0.5反、米が1.2haくらいですね。
米は作業委託を活用しているので、メインの仕事はアスパラガスです。
労働力は、アスパラガスの収獲は私とパートさん6名前後、選別は妻を中心に出荷調整のパートさん3名前後に来てもらっています。



アスパラガス中心の栽培にシフトしているのですね。
アスパラガス栽培に関して、他の産地と異なる点はありますか?



他の産地では朝夕の2回収穫が多いですが、大田原市のアスパラガスはピーク時でも朝のみ収穫です。
瑞々しい状態で出荷できるので、大田原市のアスパラガスは甘いと言われます。





鮮度がいいアスパラガスはおいしいですよね!
あとは、現在の販路はどんな感じですか?



アスパラガスに関しては、JAが4割、YOZE FARMの名前で3割、その他卸業者やふるさと納税などが3割くらいですね。
米に関しては、全量直販で売っています。



なるほど。
現在は栽培や販路をしっかり確立されているのですね。
今の経営に至る過程で、栽培面で失敗したことはありますか?



今でも失敗していますが、特に就農当初は失敗が多かったです。
アスパラガスは苗を植えてから本格的に採れだすまで3年かかると言われていますが、私は5年かかってしまいました。
灌水の管理や土を団粒化させる基本ができていないのに、自己流を加えてやろうとしたのが原因だと思っています。



やっぱり地域の栽培の基本は、理にかなっているのですね。
思ったほど収量が伸びずに、心が折れませんでしたか?



まあ落ち込みはしますけど、採算ベースを最低ラインに設定していたので、大幅に売上予測を下回ってショックを受けるということは少なかったですね。
栽培は失敗から学び、アスパラガスの面積を徐々に増やしながら試行錯誤していって。
2020年頃から全体の収量の見通しができて、ようやく収入面の不安は少なくなりましたね。



収支の最低ラインを設定しておくのは、精神的な余裕にもつながるのですね。
栽培に関して、課題や目標はありますか?



栽培に関しては、規模拡大や売上増加には興味がありませんね。
栽培技術はいいと思えるものは取り入れつつ、今が適正に近い規模と働き方だと思っているので、このバランスが保てるようにしたいです。
今後の目標や就農希望者に対してのアドバイス



後藤さんと同じように、サラリーマンを辞めて親元就農される方にアドバイスがあればお願いします。



悪い結果も全て自分の責任で収入に響くのは、覚悟しておいた方がいいですね。
責任やリスクをふまえた上で、あとは作物も労働時間も自分が思うように農業をしたらいいと思いますよ!
人間関係のストレスはサラリーマンより少ないでしょうから、生涯にわたる仕事としては農業はアリだと思います。



ありがとうございます!
最後に後藤さんの今後の目標を教えてください。



うーん、どうだろう。
死ぬ直前まで農業ができているのが、私の理想かもしれないですね。
当然今のように体は動かないでしょうけど、体力の低下や病気に気をつけながら、これからの人生の後半戦を謳歌したいです。





参考になりました。
取材させていただき、ありがとうございました!
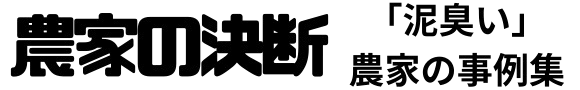
コメント