サラリーマン→東京都三鷹市の農家に婿として就農
引き継いだキウイの技術と、改善した作業工程
引き継いだ顧客の信頼と、改革した販売方法
東京都三鷹市のよしの園代表の吉野均(よしの ひとし)さんに、就農の経緯の経緯や栽培や販路で改革したこと、都市型農業ならではの戦略について伺いました!
食品スーパーのスーパーバイザー→東京の農家に婿入り
 管理人
管理人吉野さんはどんな学生でしたか?



東京の大学の経営学部に進学して、元々興味があった「卸売業」のゼミで勉強をしていました。
時代が変化しても、食べるものは絶対になくならないですから、食品関係に興味があったんですよ。
就活も食品卸や食品小売を中心にして、大学卒業後には埼玉県に本社のある食品スーパーに就職しました。



なるほど。
食品スーパーでは、どんな仕事をされていたのですか?



店舗勤務を5年した後は、バイヤーと店舗を結ぶ「スーパーバイザー」という役職をしていましたね。
売り場のレイアウトなども、他の店舗などを視察して改善していました。
順調に昇級もしていましたし、仕事も充実していました。
販売すること自体が、私は好きだったんでしょうね。



そんな充実していた仕事を辞めて、農業をすることになった経緯は何だったのですか?



結婚した妻が、東京都三鷹市の農家の長女だったんです。
農業の後継者がいないということで、私が名字を変えて婿入りして、農業をすることになりました。
東京都農林総合研究センターで1年間、栽培や農業基礎を学んだ後、2015年から義父の元で農業をしています。



婿入り就農、なかなか珍しいですね。
就農した時には、周囲からはどんな反応がありましたか?



職場の同僚には、
「一部上場企業のサラリーマンを辞めて農家になるの?しかも東京で?」
と、安定を捨てて農業をすることに、驚かれました(笑)。
そういう私も、当初は農家になることがイメージできていませんでしたね。
子どもの頃に親戚の畑に行って、たまに遊んでいたくらいなので。



農業に縁がなければ、イメージも湧かないですよね。
農業に気持ちが向いた瞬間はあったのですか?



婚前に義父がキウイをパカッと手で割って、「食べてみな」と渡されたキウイを食べさせてもらった時ですね。
昔食べたキウイが酸っぱいイメージがあったのですが、義父のキウイがビックリするほど甘くて美味しくて!
「東京でも、こんなに美味しいキウイが作れるなんて!自分の販売経験を活かして、この感動を多くの人に伝えたい!」
と、農業への道にキウイに導かれた感じがしましたよ。



お義父さんのキウイが、農家への道の第一歩だったわけですね。
吉野さんはサラリーマンと農家、どのような違いがあると思いますか?



サラリーマンでも責任も目標もあり、大変なことも多いですが、どこか会社に守られている部分はありますよね。
農業の場合、目標などは自分で設定するので、手を抜こうと思えばどれだけでも楽ができます。
ただ成果も責任もダイレクトに己に返ってきますし、最後は誰も守ってくれません。
そこが農業の厳しい所でもあり、楽しい所ではありますけどね。


GAPを元に改善した作業工程と、引き継いだ栽培技術



それにしても、田舎暮らしの私からすると、東京の三鷹に農地があるというのがイメージがつかないのですが。



まあそうですよね。
東京都の三鷹で農業をしていると言うと、今でも驚かれます(笑)。
だけど三鷹市は、マンションや幹線道路がある中に、畑も点在しているんですよ。



へえ、都会の中にも、農地もちゃんとあるのですね!
それでは、現在のよしの園さんの栽培状況はどんな感じですか?



キウイを80a、栗を10a、ミカンを10aほどですね。
労働力は、義父と私の二人です。



キウイがメインの作型なんですね。
栽培のこだわりや、吉野さんが就農してから変えていったことはありますか?



うーん、栽培のこだわりはないですかね。
当たり前のことを当たり前にやっているだけだと思います。
頻繁に畑に行って、樹の病害虫を観察して、最小限の農薬散布に留めることは意識していますけど。



その上で私が変えた所は、東京都GAPを取得して、栽培や作業工程を仕組化したことです。
特に作業場は、乱雑に置かれていた肥料や資材を整理整頓しました。
使っていない農機や資材は処分して、使う頻度や作業導線を考えてモノの配置をガラリと変えたんです。



都のGAP認証ですか。
経営にはプラスになるとは思うのですが……、
作業場の整理整頓は特に、お義父さんはやり方を変えることに抵抗がありそうな……?



たしかに義父は長年使ってきた作業場を改善することは、納得いってなかったようですが、
「作業場もGAPの審査対象だから、この配置をキープしないとダメだ。」
という大義名分で協力してくれて、効果を感じていくに連れてアイデアも出してくれるようになりました。
「孫のために」という言葉も効果的でしたね。
そのおかげで、欲しいものを取り出すスピードや出荷調整時間は、格段に短くなりましたね。



なるほど、親子間で言い争いになりやすい作業場の整理整頓は、制度という大義名分を利用すればいいのですね!
参考になります。
あとは失敗談も聞きたいのですが、吉野さんは栽培面で失敗はありましたか?



就農初年度に、手痛い失敗がありましたよ……。
研修で習ったことを持ち帰って、キウイの剪定をしたのですが……、
剪定を強くやりすぎたのか、キウイの収量は前年から約4割減ってしまいました。
1本1本の樹によって樹勢は違うので、教科書通りやればいいわけではなく、それぞれの樹に合わせた剪定をしないといけないんですよ。
「自分は研修を受けて知識があるんだ!」
と、勘違いしていたんだと思います。



「現場が一番の教科書」とも言われますが、やっぱり長年畑と樹を見てきた農家の判断が正しいことが多いんですよね。



おっしゃる通りで、義父も私の剪定を見て、失敗するだろうと確信はあったと思います。
だけど義父は、私が失敗した後も何も言いませんでした。
私も次年度からは反省して、義父の剪定のやり方を観察して真似て。
義父も私の質問に丁寧に答えてくれました。
私が失敗したキウイの樹も、年々収量は回復していったのを目の当たりにして、義父の栽培技術の高さを改めて知りました。
当初は義父と婿という意識があったのですが、現在では義理という文字が取れて、本当の父親のように感じています。



よしの園の中で、信頼関係が生まれた出来事だったのですね。
あとは温暖化対策についても聞きたいのですが、高温によって栽培への弊害は出ていますか?



酷暑はキウイにとっても厳しいですよ、本当に。
今までは夏でもなんともなかったキウイも、気温が高すぎるせいで、日焼けしてしまうようになりました。
日焼け対策としては、日当たりが良すぎる所のキウイには、傘掛けをするようにしています。



加えて経費高騰も、毎年の悩みの種です。
キウイの冷凍花粉をニュージーランドから輸入しているのですが、ここ数年で2万5000円が5万円と、約2倍になりました。
その他の色々な経費も、年々値上がりしていますから、経費高騰分を吸収できるような販売を考えていかないといけません。


義理の父が築いた顧客との信頼に、販売方法を変える



販売の話になりましたが、現在のよしの園さんの販路はどんなかんじですか?



庭先とネット直販で5割、JA系列の直売所とスーパーに4割くらいですね。
残りの1割は飲食店に卸しています。
ありがたいことに、義父の代から固定のお客さんがすでに多いんです。
年末のお歳暮として、キウイを注文しに家に来てくれている方もいるくらいですから。



しかし、お客さんが来る度に手書きの伝票を書くのは大変で、他の作業も止まってしまうのが難点でした。
だから私が、
①ネット直販や自販機の導入
②収穫体験の企画
を実行していったのです。
吉野さんの変革①:ネットを駆使した集客と注文、自販機の設立



まず始めたのは、よしの園のLINE公式アカウントを作り、Googleフォームから注文を受ける形にしたことです。
手書きでの伝票作成と整理が減ったことで、年末の作業が滞りなく進むようになりました。
顧客の情報管理もしやすくなり、農園の情報なども発信できるのも、良かった点です。



LINEやGoogleを活用する農家は増えている印象です。
直販をしていくには、ネットを使って手間を省いていくことが大事なんですね。



直販がこれだけ多いのはすごいです。
近所ではお歳暮としても有名なキウイなんですね!



効率的な販売という意味では、自販機を導入したことも大きかったですね。
今までは作業場前の無人販売コーナーのような形で、たぶん盗難とかもあって、思うように売上が上がってなかったんです。
販売点数と売上が管理できたことで、庭先販売の割合を増やしていけたのだと考えています。



自販機!
盗難の心配や接客がない分、売上が期待しやすいのはいいですね!
吉野さんの変革②:収穫体験の実施



あと変えたことは、キウイやミカンの収穫体験を企画していったことですね。
東京三鷹市は大消費地ですから、半径500メートル以内に見込みとなるお客さんを巻き込めるようにしたいと考えました。



「対面販売」形式は、販売の経験がある、吉野さんらしい考えだと思います。
実際に収穫体験をしてみて、どうでしたか?



歩いて来れる所に農園があって、普段農業に馴染みのないご家族に収穫してもらうことは、都市農業ならではだと思いましたね。
こちらとしても出荷調整の手間も省けますから、今後もいろいろな作物で収穫体験を企画するつもりです。
それにやっぱり、笑顔でありがとうと言ってもらえるのはうれしいですから。



消費者との距離の近さは、都市農業の魅力の一つですね。



販売方法の工夫は、義父の栽培技術と今までの信頼があってこそだと思っています。
私もよしの園の後継者だと認められるように、技術を磨いていかないといけないと、改めて感じました。


目標やアドバイス:都市型農業の宿命と向き合う



吉野さんのように、就農を考えている方にアドバイスをお願いします。



経費高騰や酷暑などの不安材料も大きいですが、それはチャンスと捉えた方がいいです。
米騒動で見られるように、全体的に農作物の価格は上がっていますし、「食」は絶対になくなりませんからね。
栽培も販路も、工夫次第でチャンスはあるはずですよ。



ありがとうございます。
最後に、吉野さんの今後の目標を教えてください。



今後の目標は、農業を次の世代につなげていくことです。
というのもよしの園の農地は生産緑地で、相続発生時に農地を売却して、多額の相続税を納める可能性があるからです。
相続税の納税猶予を受けることはできますが、それには後継者が農業を続けるという必須条件があります。
私は、変わりゆく都会の中で、農家であり続けるという宿命があると思っています。



私の息子もいずれ、農地の相続の対象になるでしょう。
もし息子が何十年後かに、
「農家になってもいいかな。」
と思ってもらえるように、栽培や販路、作業環境や経営の仕組み作りをしていくのが私の人生の目標ですね。



取材させていただきありがとうございました!


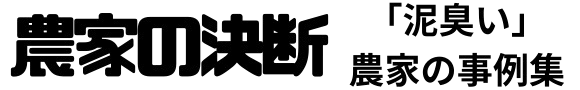

コメント